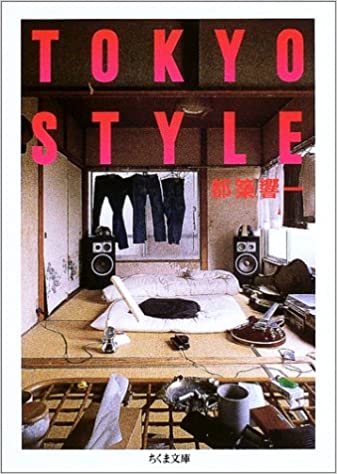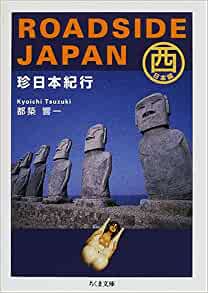Interview by 有太マンYutaman Photo by Keita Suzuki鈴木啓太
2012年7月にRiddimOnlineに掲載された記事です。
都築響一氏は編集者であり、第23回木村伊兵衛賞受賞カメラマンだ。80年代の「POPEYE」、「BRUTUS」にはじまり、京都書院から出た全102巻に及ぶArT RANDOMシリーズ、写真集「TOKYO STYLE」や「ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行」等々、これまで関わり、世に出してこられた雑誌、作品は枚挙に暇がない。
近年もラブホテルやスナック、暴走族等と、ずっと私たちの生活と共にあったものに新たな切り口を与えてきた都築氏。氏の最新の仕事の一つが、昨年5月から続く連載「夜露死苦現代詩2.0 ヒップホップの詩人たち」だ。
媒体は月刊新潮。毎号約20ページもの大ボリュームで展開される連載は初回のILL-BOSSTINOにはじまり、これまでB.I.G. JOE、鬼、田我流、RUMI、TwiGy、ANARCHY、TOKONA-X、小林勝行、チプルソ、ERA、志人、NORIKIYOが登場してきた。
日本語ラップの今を「30年前にヤンキーが生み出せなかったリアルなストリート・ミュージックを、今ようやく、最良のかたちで生み出しつつあるのかもしれない」と紐解き、それに肉迫し、記録する自らの「スリルを押さえることができないでいる」と語る都築氏に聞いた。
●連載の書籍化も視野に入ってこられたでしょうか。
都築響一(以下、T) 連載はあと2回くらいでお終いにして、年内には単行本にできるんじゃないかな。最終的には一年半まで行かない、16回か17回でお終いという感じです。きりがないし、あとは相当量の原稿なので、これ以上やっても一冊が厚くなり過ぎちゃうので。
●話を聞きに行きたいラッパーはまだまだいますか?
T:そりゃあいますよ。でも僕なんかは、ヒップホップの話で言えば完璧に部外者なわけです。ただの素人で、他のロックや色んなものと同じくヒップホップも好きだったんですが、作品やライブの情報やなんかが「あまりにも整備されていない」という気持ちが強くありました。それから「聴いてみれば面白いのに」ということもあって、全然違う媒体で、ヒップホップのことを知らない人たちに読ませたかった。あとは、ページ数をたくさんとれる媒体がああいう雑誌しかないんです。
●毎回どれくらいのボリュームなんですか?
T:2〜3万字なんじゃないですか。インタビュー・パートだけで一万何千字で、それにリリックが入ってきますので。しかし繰り返しますが、僕は部外者なわけです。僕はこれをやらせてもらって楽しいですけれど、「中の人たちは何をやっているんだろう」という気はいつもしますよね。これは僕じゃなきゃできない話じゃなくて、中の、ヒップホップ・ワールドにいる人ならもっと簡単にできることなんです。だってこっちはツテもほとんどなく、ホントに電話番号を探すところから始めなきゃいけなかったというね。
●部外者、素人と仰られますが、連載にはグランドマスター・フラッシュのリリックとの比較が出てきたり、AUDIO SPORTSの92年の音源で、初めて録音されたTwiGyさんのラップを当時に確認していたり、深い造詣を垣間みることができます。
T:それは歳だからですよ(笑)。僕は今56歳で、取材を始めた頃にレゲエもヒップホップも出てきた時代だったから。
●ヒップホップとの最初の出会いは?
T:80年代のNYです。「POPEYE」や「BRUTUS」でNY取材をやっている時にちょうど出てきたものだから、最初から見ています。それこそSUGARHILL GANGとかそういう頃で、当時の方がヒップホップは開かれていたと思うんです。だってヒップホップしか聴かない人なんかいなかった。ディスコも聴けば、ヒップホップやロックも聴くみたいなことの方が多かったし、だから僕も聴いていた。それが今や専門分野になってしまったもんね。だって例えば、NYの街を取材する時に「端っこのところで、変な面白いディスコやってるよ」というのがパラダイス・ガラージだったりして、行ってみるとアマチュア・ナイトにマドンナが出てたとか、そういう時代でした。ヒップホップも「盛り上がりの中の一つ」という感じで、それから比べれば「遠くへ来たもんだ」っていうね。だから確かに経験はありますよ。
●それから20年以上の歳月が経ち、改めてヒップホップに興味を持つようになるきっかけは?
T:この5、6年前に「夜露死苦現代詩」のオリジナルのやつをやって、その時もヒップホップもちょっとだけ入れたんですね。その時は日本ではダースレイダーさんをやって、あとはエミネムとかもやりました。ダースレイダーさんはね、音楽もそうだし、売り方が好きだったんです。DA.ME.RECORDSというのをつくって全部1000円でやるっていう、業界の中でサバイヴしていくやり方も面白かったし、内容も、当時はギャングスタ系が多かったと思うので、そういうのと全然違う感じもあった。すごいちゃんと話してくれましたし、面白かったので良かったんですけれども、当時から「もうちょっとちゃんとヒップホップをやりたいな」というのがあったんです。
●それからまた年月が経ちますね。
T:でも誰も友達で詳しい人もいないので、ひたすらCDを買ってました。もう山のようにありますよ。わかんないから、全部買うしかなかった。
●そして、満を持して連載開始に至ると。
T:それは、その時代その時代で、特に若い子たちの想いっていうものを、一番確実に表現する音楽のジャンルがあるんです。それはたぶん、40年くらい前だったら、自分が「あぁ〜!」と思ってることを一番ダイレクトに表現できたのはフォーク・ミュージックだったかもしれない。そしてそれがパンクだった時は、「とにかく3コードさえおさえればいけるぞ」みたいなことでいけたと。そもそもの最初に、僕の地方巡りの仕事っていうのがあるんですけど、地方に行くと若い子たちがつまらなそうに夜中にたまったりしているわけじゃないですか。でもそこで昔みたいに、ギターで「とりあえずFを練習するぞ」とかではない。それがここ10年ぐらいはヒップホップで、「とりあえず有りもののビートで、とにかく自分のラップをやる」と。そして、それを中学校の体育館の裏で練習するみたいな、僕は特に日本ではそうだと思ったんです。それからやっぱり、ヒップホップは他の音楽に比べて垣根が滅茶苦茶低い。だって楽器がいらなくて、マイク一本でしょう。スタジオすらもいらないくらいで、夜中の公園とかで練習できる。一番お金がなくても練習できる音楽で、だから世界中に広まったと思うんです。僕は世界の田舎にも行くんですが、昔見ていた、ロックが世界中に広がっていく速度よりもヒップホップの方が早い。だって今、イランだってラップがあるわけだし、たぶん北朝鮮にだってあるかもしれなくて、これだけ包容力のある音楽形態ってなかなかないわけですよ。中国にロック・バンドもありますが、それはやっぱり資産階級じゃないとできない。だけどヒップホップの場合は、本当にラジカセ一個あればいいということがあるので、そういうヒップホップの形態の持つ力というのがありますよね。
●それは「Roadside Diaries」なり、これまでの都築さんが仕事で地方を巡る中で見る光景とリンクする音楽として、実感があった。
T:それは日本だけでなく、僕はずっと、アメリカの50州を7、8年かけてまわるっていう企画をやっていて、それが「ROADSIDE USA」というんですが、7、8年間何回もアメリカに行っていたわけです。コーディネイターみたいなものも使わず、いつも一人でアメリカの田舎を走り、そうすると若い子はヒップホップしか聴いていなかった。そこではレディ・ガガすら聴いていなくて、ショッピング・モールの駐車場で音をかけて女の子を待ってる男の子みたいなのは、黒人白人関係なく全員ヒップホップ。だけどそれはチャートには反映されないですよね。日本でもそうだと思う。田舎で、中学生まではAKBとかを聴いてるかもしれないけれど、たぶん高校以上になるとヒップホップでしょう。だからそういう、「チャートに反映されない音楽の動きってすごいあるな」って思ったんです。もう音楽誌も読んでないので、田舎でコンビニとかに夜中に行くと、そのへんのジャージとか着た男の子たちの車の中でかかってる音楽とか、そういう方が気になりますよね。
●都築さんのお仕事で一貫しているのは、「それまで価値がなかったものに新たな価値を与える」作業であるような気がします。その編集の手腕に加え、さらにご自分でカメラとペンも持たれると。そのDIY精神みたいなところで、ヒップホップの若者たちとのシンパシーもありましたか?
T:それもありました。でも僕がやっていることは、別にもう一つ「絶滅危惧種の記録」みたいなこともありつつ、大きなことは「本当はこっちの方がマジョリティなんだけど、メディアには出てこない」ということなわけです。例えば、東京に住む人の9割は家賃10万円くらいのところに住んでいると思うんだけど、インテリア雑誌にはそんなことが出てこない。そういうところでやっているし、だから本当は、ヒップホップもそうだと思うの。つまり、みんながちゃんと聴いてるのはヒップホップの方が多いってケースもあると思うんですよね。だってブルーハーブのコンサートなんかすごい人が来るわけじゃないですか。あんなに危険を感じるコンサートはないってぐらい、みんな動けないし、何か落としてもとれないまま3時間くらい待ってるもんね。
●夜中の汗だく、ぎゅう詰めのライブに、55歳を超えた都築さんが行かれるわけですね。
T:行きますよ。もう「身の危険が」っていう(笑)。しかもパスなんかもらわずに、お金払ってね。
●そしてUMB(ウルティメイト・マイク・バトル)にも行かれると。
T:マイク・バトルの時って、自主制作のCDが一番買えるんです。でもね、別に僕はヒップホップだけがいいと思ってるわけじゃないですが、こんなに若者たちが好きで聴いているのに、他の雑誌に出てこないのはもったいないなって純粋に思うんです。だから僕ができるんだったら僕がやると。それで、他の雑誌ではレビューは書けるでしょうけど、歌詞を載せられないじゃないですか。でもこれ、歌詞を読んでくれないと本当の良さはわからないと思うんだよね。
●まずは歌詞を読むべきだと。
T:でも、みんなお金がない中でつくっているわけだから、CDを買っても歌詞カードがない場合が結構ある。さらにはアーティストが歌詞を持ってないケースもある。だからこっちで聴き取って、わからないところをアーティストに埋めてもらうみたいな、とてつもない作業もやってます。でも本当は音楽雑誌がそれをやって欲しいんだよね。そしたら僕みたいな部外者がこれをやる必要はなくて、それを読んでいればいいわけです。あとはね、この中にはブルーハーブにはじまり、結構ヒップホップ界で有名な人が出ていますよね。だけど大体全員が、「こんなにちゃんとした長いインタビューを受けたのは初めて」って言うんです。今まで「今度のアルバムどうですか?」って話はするけれど、「じゃあ小学校は?」みたいな話ってまずしなかった。あとはステージ写真もなるべく撮りに行くんですが、「ステージ写真ください」って言われるケースも結構ありました。だからヒップホップではそれくらい、メディアが遅れてるんでしょうね。こんなにファンはいるのに何なんでしょう。だって、雑誌じゃなくてWEBマガジンでもそれなりに広告は入るだろうし、成立すると思うんです。でも何もない。僕はそれに一番びっくりしましたよ。それは媒体があまりにもないということと、すごい有名アーティストでも、きちんとした、事前に読んでおけるようなインタビュー素材がほぼないということですね。
●そして、連載の最初には「崩れていく東京の権威」について言及され、「今一番面白い音やシャープな詩を書くアーティストはほとんど地方にいる」とされています。
T:日本のヒップホップが気になってきたのは、本当に地方を巡ってということもありますし、東京に出てこない子たちもいるわけで、地方じゃないと買えないCDもあるわけでしょう。聴いてるとずっと思うのは、ヒップホップは都会の音楽じゃないですよね。でも田舎の音楽でもない。郊外の音楽なんですよ。サバーバン・カルチャーであって、大自然が生んだ音楽じゃないし、もの凄く都会的でもなく、都市の中心からちょっと外にあるんだけど団地街みたいな。それはアナーキー然り、本当に団地出身ってすごく多いじゃないですか。
T:日本ならプロジェクト=公営団地みたいなものですよね。だから面白い日本のヒップホップを聴いてるとね、その郊外感覚というものがすごいあります。そういうのっていうのは、都市の一番先端に行こうとしてきた人たちとはなかなか違うセンス。だからそういうのがわからないと取り上げ難いのかなという気はします。逆に、音楽の流行の先端はもうちょっと違うところにあると思います。そうじゃなくてヒマしてる子どもたちの、でも農作業まではしなくてよくて、金はないけどすごくないわけじゃないっていう、そういう気が、体験的にはしますよね。
●すぐ脇に都会を見つつ、そのちょっと外にいるという。
T:実家率高いしね。何なんでしょうね、あれは(笑)。なんとなく実家があって、なんとなくすごい働かなくてもいいのかもしれない、そういうメンタリティってあるのかなという気はしますね。
連載には社会不適合者というか、不良と同時に引き蘢りがちな子も出てきたりします。彼らの受け皿としてのヒップホップみたいな側面もありますか?
T:でもすべてのアートってそうあるべきですからね。音楽に限らず、例えばポップ・アートだってそうだったわけで、例えば60年代のイギリスとかでは大学に行けない子たちがアート・スクールに行って、そこでミック・ジャガーとキース・リチャードが出会ったりするわけですよ。そういうところからポップ・アートも生まれたりする。だから本当は絵も音楽も、いいコースに乗れない人たちの救いの綱じゃないといけなかったと思うんですね。それがだんだん大きくなってビジネスや業界になっていくわけだけれども、出だしは常に、そういうはみ出しものがつくっていかないとやっぱりアートっていうのは面白くない。それが今の時代はヒップホップかもしれないということですよね。
●逮捕歴のあるラッパーも普通に登場します。
T:だからといって別に色眼鏡でみるわけじゃないし、逮捕歴があるから偉いわけでもない。もう、一時みたいに「悪いこと自慢」でもないと思うんですね。それにそういうことをやっていると、ヒップホップという音楽が、悪い人が好きな人にしかアピールしていかなくなってしまう。もっと日常のことを歌えるようにならないと広がっていかないわけじゃないですか。それは例えば、夜中の3時にライブ・ハウスに行ける人は限られているように。だから色んな形態の詩の内容がないとおかしいと思うし、ワルだから偉いわけでもなく、でもワルだから閉ざされるというわけでもないところは、逆に言えばある意味ヒップホップが成熟してきたってことだと思います。つまり今まではもうちょっとワンパターンだった。悪いことをして、金があって、アメリカでつくられたある種の理想像みたいなものが、そのまま入ってきたわけじゃないですか。でも日本でシャンパン、コーク、リムジンという人はまずいない(笑)。あまりにリアリティないだろうっていうので、バイト生活で大変な毎日とか、そういうのを歌えるようになってきたというのが、表現として次の段階に来たっていう気がして。だから僕もこういう企画をやりたかったのかもしれないですね。
●地方の疲弊と中央の関係性みたいなことに関しては、例えば田我流と「サウダージ」という映画はその典型かなと思います。
T:でもね、たぶん、地方は疲弊っていうほど疲弊してないんだよ(笑)。僕はそっちの方がポイントだと思います。東京から見ていると山梨は疲弊しているかもしれませんが、僕はそうやって地方の取材することもすごい多いけど、それこそ「サウダージ」に出てくるようなシャッター商店街でも、地方のおっさんたちにそんな危機感はない。東京から見て「これどうすんの」みたいな話になるんだけど、大体あれも2階に人が住んでるわけですよ。田舎の人はそれほど危機感は持ってなくて、むしろそっちの方が問題だと思う。
●文句を言う前にやれることがあると。
T:この間は大牟田のクラブに行って来たんです。昔は三井三池炭坑という日本有数の巨大炭坑があって滅茶苦茶盛り上がったんですが、今は超シャッター商店街とシャッター・スナック街と化している。その中の十何年前に潰れたキャバレーを地元の子たちが借りて、そこにDJ入れたりして、ライブとかもやってるわけですよ。ノイズ・バンドとかが出て、高校生がそれを観に来て、夜の10時過ぎとかに制服でモッシュとかしてるわけ。セーラー服でそこら辺に転がったりしてて、こんなの東京だったら即補導とかクラブ閉鎖みたいなことでお終いなんですが、音もダダ漏れで、全部シャッター商店街だからそれもどうでもいいと。だからやれることはたくさんあるんですが、でもそれでも何も出てこないのは、田舎の方がメンタリティがぬるいんです。だから一概に、地方が疲弊してるから、反抗の中からヒップホップ出てきたというのとはちょっと違う感じが、感覚的には僕はします。
●あえて逆に、部外者の立場だからこそ、ヒップホップの世界にアドバイスみたいなものはありますか?
T:やってる人には全然ないです。みんな頑張ってますし何もないですが、周辺の人はもっとサポートしてあげないとなと思いますね。今雑誌を創刊するのは大変だしお金がかかるけど、WEBだったらタダでできるわけじゃないですか。メールマガジンにするとか何でもいいから、やっぱメディアがないとダメだと思います。そうじゃないと、レコード屋に通ってフライヤーにチェックするとかしかできないもんね。それ、一番アナログでしょう?それでクラブ潰しとか言われてますけど、別に普通の夕方やればいいわけですよ。夜の8時とか9時にやればみんな来れるし、ちゃんと終電で帰れる。そうすれば風営法も何の問題もないんです。だって昔のディスコは大体12時にちゃんと終わっていたもん。椿ハウスだって何だって、ジュリアナだって12時に普通だったらお終い。もっとやりたい人はアンダーグラウンドでつくればいいわけで、文句言ってるより、できる時間帯にやればいいだけのことだと思うんだよね。次に連載に出てくる子も、昼間働いている子なんですよ。だから「クラブ行かないです」って言ってたもん。「朝から仕事あるし、ライブを夕方やってくれればいいですけど」って。
●やってる当事者からもそういう要望があると。
T:だって始発で帰るってことは次の日無いわけでしょう。普通の生活をしている人は無理ですよね。
●そのハードルの高さが文化を鍛え上げたという側面は?
T:あるとも思うけど、デメリットも多いと思います。ライブを観に行けない。CDもなかなか買えない。包括的に情報を得られるサイトもない。ということは、どんどん内に内に閉じていっちゃってると。配信とかでシステムはどんどん外に開かれて、お金をもらうシステムも自分たちでできるし可能性は広がっているのに、「どうせオレたちの音楽はわかるやつにしかわからない」という感じで閉じていくのは、すごいもったいないと思うんです。