|
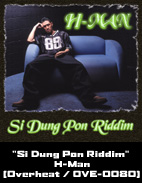 「ジュリー(沢田研二)になりたかったんですよ」という、ある意味普通の音楽少年として育ったH-Man。ボブ・マーリーと出会ったのを機にレゲエの入口を潜ったところまではよくある話。しかし、その後のイエローマンにヤラれて、ダンスホールに夢中になり、やがてランキン・タクシー等の日本人DJの存在の影響も受けて、自らマイクを握るようになったところから本格的に本人言うところの″レゲエ馬鹿″人生が開始する。それが10年前、そこ藤沢にはムーミンも居た。 「ジュリー(沢田研二)になりたかったんですよ」という、ある意味普通の音楽少年として育ったH-Man。ボブ・マーリーと出会ったのを機にレゲエの入口を潜ったところまではよくある話。しかし、その後のイエローマンにヤラれて、ダンスホールに夢中になり、やがてランキン・タクシー等の日本人DJの存在の影響も受けて、自らマイクを握るようになったところから本格的に本人言うところの″レゲエ馬鹿″人生が開始する。それが10年前、そこ藤沢にはムーミンも居た。
「なんでだろう? うーん、レゲエが俺を受け入れてくれたからかなぁ。自分が出来るやりたいことが(レゲエに)あったという感じかなぁ」。
マイクを握り始めた頃、メッセージを高らかに歌う″闘う″DJのスタイルにも憧れたが、「そんなことをいっつも考えているわけじゃないのに、そんなことは言えない」とあっさりと見切りをつけ、現在に繋がる″笑かす″スタイルを追求していく。
「元々二枚目じゃないし、笑かすというか、そういう楽しいのって好きだったしね」、あと「笑わせた時の盛り上がりは結構万国共通というか、マッシュ・アップ(盛り上がる)という感じになるじゃないですか。自分がジャマイカのDJみたいにやるのは無理なんだけど、ジャマイカのDJがジャマイカの観客をマッシュ・アップする、そのジャマイカでのマッシュ・アップと同じ様な状況(空気)を日本でも作れるんじゃないかと思ったんだよね」。以来、常に現場をマッシュ・アップすることだけを頭にマイクを握ってきたH-Man、
「お客さんが少なくて盛り上がるような空気じゃないところでも、なんか面白いことを言えば聞いてくれるというか、なんだ??と思ってくれるかな、と言うのもあったんだけど…。結局、ダンスなんてみんな嫌なことを忘れて楽しみに来ているのに、テレビのニュースで言っているようなことを俺が言っても意味ないし、ねぇ? だって楽しいって良いじゃない?
」。
「あと、お客さんを盛り上げることに、自分自身と社会との接点を見い出すというか、自分の存在理由があると感じるからねぇ」。
さて、その記念すべきデビュー作は、マキシ・シングル仕様。タイトル曲の「Si
Dung Pon Riddim」(シドン・パ・リディム)に加え、同時収録の「Bombo Claat Talk」(ボンボクラ・トーク)は共にライヴではお馴染みの人気チューン。まずは代表曲で顔見せといったところか。しかし、「Si
Dung...」は "Flex" 調、そして「Bombo...」はナイヤビンギを使用したダブ・テイストなトラックで、どちらもライヴで聴く印象とはかなり異なった仕上がり。けど、結果的にはこれが逆にH-Man独特のリリック・センスと、耳に絡み付くようなあのフローを引き出し、よりH-Manとしてのスタイルを全面に提示した絶好のデビュー作品となったと言える。
「この2曲でというのは自分の選択。で、"Si Dung..." はタンコとコンケン(ホーム・グロウン)に、それと
"Bombo..." はリトル・テンポとかのドラムやってる大石さんがトラック制作。どちらも自分で完成形を頭で描いてやって貰ったから全く問題無し。やっぱりそれぞれの曲に合せてトラックを作るってのは良いな、と。でも、トラックよりも自分が目立つという方が当然大事なんだ」、と本人の手応えもガッチリ。
「皆へのメッセージ? まぁ、笑ってくれるだけで良いんだけど、これでリリックの行間というか、そこに込めたメッセージみたいなものも伝わればそれはそれで嬉しいかな。それとやっばりこれ聴いてライヴに来て貰いたいネ。これ出すのもお客さんがライヴで知っている曲があった方が盛り上がれるだろうと思ったところもあるから」。
ステージで見る印象とは少し違ったH-Man、意外にも(?)とっても真面目な人でした。
|


