|
日本のダンスホール・レゲエの創始者と誰もが認めるランキン・タクシー。彼が80年代に見たもの、経験したもの全てがダンスホールと言っても間違いないだろう。それなら80年代の日本のダンスホールは、彼に語って貰うしかないでしょ。
レゲエと出会ったのはもっと前ですけど、ジャマイカでレゲエと出会ったのは私としては83年。日本人は喜び方をジャマイカ人に学んでるんだから。熱狂の仕方を。(机を)バンバン叩いて喜ぶとか、椅子ガチャガチャやったり、壁叩くとかさ。それも良い音で鳴らすよな。最初はそういうものにまで感動してたからな。情報がなかった分、何見ても「スゲー、スゲー」っていう。目の前で腰が動くっていうのも凄いな、結局全てに感動しちゃうんだよな。
 70年代からボブ・マーレーを聴かされたって感じなんだけど、なんか心に食い込んでこなかった。それと違う物が現れたのがイエローマンでしたね、私にとっては。それ以前にダンスホールをやってたのは、タクシー・レーンっていう店がバブリン・ダブに名前を代えた頃、そこで雇われ店長をやっていたサッタ君ですね。今、栃木で農民やってますけど、彼の周りっていうとマッチャンっていうのとかいるんですけどね。大体ワン・ドロップなんですよね。 70年代からボブ・マーレーを聴かされたって感じなんだけど、なんか心に食い込んでこなかった。それと違う物が現れたのがイエローマンでしたね、私にとっては。それ以前にダンスホールをやってたのは、タクシー・レーンっていう店がバブリン・ダブに名前を代えた頃、そこで雇われ店長をやっていたサッタ君ですね。今、栃木で農民やってますけど、彼の周りっていうとマッチャンっていうのとかいるんですけどね。大体ワン・ドロップなんですよね。
それでその当時、真似事みたいのをやってたのが西荻で工藤″純情″晴康ですよね。それと横浜で84年からはじめたランキン・タクシーが真似事をしていたって事ですよね。
だけどガッチリとサウンド・クオリティーを伝えられるって人もいなかったし。その当時のクラブと言えばピカソ、トゥールズ・バーですが、まだサラリーマンをしてたんであんまり夜遊びは出来なかったんですけど、私はやっぱりレゲエ絡みのイベントがライヴハウスとかクラブである時に顔を出してましたね。
他の音楽と比べてどうのっていうバランスが見えないんだけど、その時は(レゲエのパワーに)ショックを受ける人がドンドン増える方向で、勢いのあるジャンルとして捉えられてたと思うんですよ。大きな存在がボブ・マーリーだったから、レゲエを回してると知らない人が来てボブ・マーリーをリクエストするっていうのは多かったですよ。クラブ・ジャマイカが出来た時もそうだったからね。そう、ここを作った菅井さんとセレクターの佐川修たちの功績は大きいよね。それでその当時のセレクターは男の美学みたいな感じだったと思うよね。
その頃、日本語でダンスホールをやっている人はいなくて、(俺の)「俺といて」、それから「いいかげんにしねえと怒るぜ俺は仏の顔も三度までエエ」っていうのがね(初めてだった)。あと意外に「ひとかけらのチョコレート」も早い時期だったかもしれないな。それが84年とか。その前に日本語でダンスホールをやっていたのはいないでしょ。
で、ナーキが次。ナーキは一橋大学の時は歌えてDJも少し出来てピアニカも吹いていた。それで当時は加藤学の仕込みもあったのでスタジオ・ワン系のカヴァーが多かったと思います。彼は日本語でDJはやらなかったけど、ユース・プロモーション系DJの口真似はしてたと思う。実際、口真似から入らない奴は嘘かなって気がするんだよね。
それから口真似って言えばチャッピーだね。俺がチャッピーを初めて見たのは、確かサルパラダイスに彼が来た時ですからね。彼が突然「やらして欲しい」って来てね。それでやらせてみたら、「真似が上手いじゃない」ってね。当時は日本語でもやってたんですよね。「クラリネットがこわれちゃった」とかね。
大阪方面はセント・アンズの事は忘れられない。京都のミ・アイとカーティス・フライ、それからうちのトッシュって奴を連れて回ったのが87年かな。アッ、ブギーマンもやってましたよ。そのツアーに連れてってくれって言われたんだけど「ちょっと若いから」って言って断ったんだよな。それ87年でしたよ。
あの当時はゼブラマンとかディックマンっていう神戸の馬鹿野郎達ですね。この馬鹿野郎達も87年ごろには動きはじめてますよ。「六甲山に猿が出た」とかそういうネタをやっていましたから。海の物とも山の物ともつかないんですけど、今も同じような感じで妖しい感じをレゲエの中につかんでいたんだなって。
俺も感じるんだけど、そういうのを再現したいって思う奴が出てくると面白いんですよね。そういう意味では大阪ではドラゴン・ターボ、同い年なんですけどね。まぁ似たようなとこに目をつけてたと思うんですけどね。その位のポジションでDJをやってた奴が80年代の後半になるとボツボツ出てきますよ。ブギーマンも87年位には始めていたよね。ブギーマンがその時若手だったって事か…。ナンジャマンが88年のジャマイカにサンスプラッッシュに行くツアーでお客さんだったからね。シブヤ(サンダー・キラ)とね。
クラブ・ジャマイカはギリギリ80年代だったけど、80年代はレゲエ・シーンって殆ど無かった。あとね、俺、テレビの番組でタモリと南こうせつが冗談で黒いドレッドの帽子を被って二人でゴロンボとかボロンゴとかっていう名前で冗談のレゲエやってたのテレビで見てますよ。世の中で見てる奴はさ、ドレッドだとかレゲエのおじさんだとかとも思わなかったんだろうけど、ダンスホールの外にもボブ・マーレーからレゲエを引きずった文化人もいる事は確かなんだよ。今は情報量が凄いですからね。あの80年代の情報量を1としたら今は一日で来ちゃうんじゃない。
80年代はダブ・プレートなんて日本で10枚位しか存在しなかった。私が最初に録ったのはグレゴリー・アイザックスとジョニー・オズボーンでしたね。それからクリス・ウェインとシュガー・マイノットに頼んどいたけど来なかったね。それが85年です。86年の最初の方にジャミーズのダブをそのままカッティングして貰って持ち帰った。あれは7インチも出てなかった。当時やってた奴は日本でどこが何を持ってて何枚あるとか知ってましたよ。大阪に何と何があって、誰が持っていてとか。今は別に当たり前だし、誰がなに持ってるかわからないですからね。大体みんな持ってるしね、今と全然違いますよ。
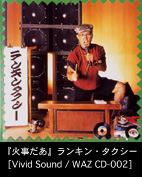 第三倉庫も80年代の終わりの頃だよな。あそこもパトロンだったよね。よくやらせてくれたと思う。それでECDが自分のテープを持って「聴いてください」とか言って。そういう風に自分のやった事をテープにして人に聴いてもらおうと思って持ってくるっていうのが凄いなって。聴いてみてまた中味が凄いって思っちゃったね。 第三倉庫も80年代の終わりの頃だよな。あそこもパトロンだったよね。よくやらせてくれたと思う。それでECDが自分のテープを持って「聴いてください」とか言って。そういう風に自分のやった事をテープにして人に聴いてもらおうと思って持ってくるっていうのが凄いなって。聴いてみてまた中味が凄いって思っちゃったね。
それでギリギリ80年代の最後、つまり89年の年末に『火事だあ』を出したんだ。でも、こんなね、80年代の話をしても、喜ぶのはオヤジぐらいですよね(笑)。
[ランキン・タクシー談]
|

