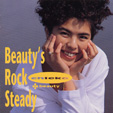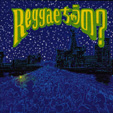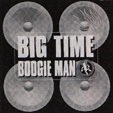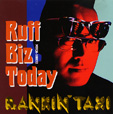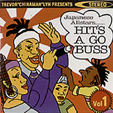|
90年代に入り、海外のレゲエ・アーティストも次々とメジャー契約をするなど、誰もが予想だにしなかった空前のレゲエ・ブーム到来。その影響もあってか、ここ日本でも次々とアーティストが誕生した90年代前半とは一体何だったのか?
「発見」そして「提示」が為された80年代後半を経て、90年代前半は「実証」の段階に突入した時期だった様に思う。
ランキン・タクシー、ナーキ、或いは「ジャパンスプラッシュ」は、それまでの僕たちの「レゲエ観/ジャマイカ観」を色々な意味で覆えしてくれた。「南の島」という以外、イメージする術すらなかったあの島で、実際″そんな遊び方をしてたのか!″的な驚きが、キングストンへの興味をかきたてる。ジャマイカへ渡航する人口は急増し、実体験者の生きた情報はいつも羨望の的だった。こうした「発見」と「提示」が、90年頃からの、初期の長期武者修行組をジャマイカへと送り込んでいった。
ジャパニーズ・レゲエも、違った2つのベクトルで動き始める。ひとつはランキン・タクシーに代表される様な、国内においての日本語スタイルを普及させようとする方向性。もうひとつはナーキ、PJの様に、いちアーティストとして、国内はもちろん、ジャマイカ及び世界を相手に、行けるとこまで自分の可能性を追求しようという方向性。どちらも「キングストン生体験」を通過しているという点で、それまで既存のナチュラリスト志向のルーツ・レゲエ派とは少し違った90年代初頭らしい動きだったと思う。いずれにしても、90年代突入と共に、このジャンルで「喰っていく」という挑戦が本格的に始まった訳だ。
ごく初期の日本語レゲエを顧みた時、最初期に重要な役割を果たしたレーベルとして「ナツメグ」の名前が挙げられる。インディーズ・メーカーとして、パンクを出発点に、当時、多くの国内クラブ系サウンドを手掛けていた同レーベルは、レゲエにおいては、チエコ・ビューティ、ボーイ・ケンといったアーティストの曲を作品化。チエコ・ビューティをソニーを通じメジャー・デビュー(『Beauty's
Rock Steady』92年6月)させる一方で、当時としては画期的なワンウェイ・コンピ『Hard Man Fi Dead』(92年9月/パパ・ボン、ボーイ・ケン、マイキー・スマート、ミニドン、ユウ・ザ・ロック、マチャコ、スモウマン、レッド・モンキー、チャッピーらを収録)を、日本コロムビアを介し発表。現場シーンの窓口となり、初期段階の底辺拡大に大きく貢献していた。こうした中で、現在のシーン形成に最も直結した動きがV.I.P
インターナショナルとの一連の作業だろう。
V.I.P インターナショナルは、最も早くに本格的に「実証」作業を始めた集団である。先達の「提示」に触発され、渡JAし、それを通じて知ったキングストンのノウハウを、国内においてシステマチックに実践に移し、レーベル、バンド、サウンド・システム、プロダクションを有機的に稼働させ、多くのアンダーグラウンド・アーティストに門戸を開いた。90年から準備段階に入り、92年7月にレーベル発足。と、同時に毎月2タイトルというハイ・ペースでアナログ7インチ盤をリリース開始。ここの「アナログ7インチ盤」という点が重要だと思う。ジャマイカの様に現場で日本人の曲をかける。それまで″歌うこと=活動の全て″だったアンダーグラウンド・アーティストたちが″自分の曲を録音物に出来る、そしてそれをクラブで聞ける″様になった。このことが意味することは大きい。その後も精力的に制作を続け、翌93年2月には、先の日本コロムビアを通じて早くもコンピ・アルバム『V.I.P
Hits 1』をリリース。矢継早に同年6月に『V.I.P Hits 2』を、更に11月には『V.I.P Hits 3』をリリースしてしまう。この3枚のCDだけで1年の間に30曲を発表(各ヴァージョンを除く)。送り出したアーティストに は、ボーイ・ケン、チャッピー、ヘイ・Z、パパ・ユージ、浪花男、ジュードーマン、ジュニア・ディー、Lt.
チョロ、ツイギー、PHフロン、チョッキー・トク、牛若丸、ムーミン、マッカラフィン、キャタピラ、ジェイソン・Xらがいる。その後、95年にレーベルごとソニー・レコード内のレーベル「G'sファクトリー」に移籍。質実共にグレード・アップしたコンピレーション『志〜The
Best Of Japanese Reggae』をリリースしている。 は、ボーイ・ケン、チャッピー、ヘイ・Z、パパ・ユージ、浪花男、ジュードーマン、ジュニア・ディー、Lt.
チョロ、ツイギー、PHフロン、チョッキー・トク、牛若丸、ムーミン、マッカラフィン、キャタピラ、ジェイソン・Xらがいる。その後、95年にレーベルごとソニー・レコード内のレーベル「G'sファクトリー」に移籍。質実共にグレード・アップしたコンピレーション『志〜The
Best Of Japanese Reggae』をリリースしている。
一連のV.I.P インターナショナルでの作業を経て注目を浴び、活動を活発化したアーティストに浪花男がいる。V.I.Pレーベルでの7インチ盤でリリースされた「インディカ」「僕、ボッキ」などで話題となり、同2曲が93年2月に日本コロンビアよりCDシングル化。同年11月に2枚目のCDシングル「銭〜っ」を発表した後、94年にはファイル・レコードに移籍。8月にはアルバム『ダディー関西人』をリリース。軽妙なトークと掴みとしての「お笑い」フレイヴァーで人気者となった。更に躍進は止まらず、95年にはソニーに移籍。ジャマイカ録音を敢行した意欲的なアルバム『ブレイクしそう』をリリースするに至った。加えるに、この時期にG'sファクトリーが果たした役割も大きい。
 ここで本誌「Riddim」の、89年末頃から95年にかけての抜粋記事をめくってみる(と言うか、さっきからずうっとこれを見ながら執筆してるのだが)。92年ぐらいまでは「チェック・ユア・マイク」や「ゴールド・チャンプ」の様なMCコンテストが盛んに開催されている。裏を返せばそれだけアーティストにとって有効な現場が少なかったのでは、とも言える。92年頃といえば、全国にサウンド・システムが急激に増殖し始めた時期だった。しかし現在の様に、各地のサウンド・クルーが全国を回れるツアー・ロードは確立されていなかったし、それだけ地方同士の交流も少なかったといえる。では、93年頃以降にこのネットワーク化を進めたものは何だったのか? それは「日本人ダブ・プレートの現場での実用化」と「セットを建造するクルーの増加」ではなかっただろうか。「実証作業の拡大」が始まったのである。 ここで本誌「Riddim」の、89年末頃から95年にかけての抜粋記事をめくってみる(と言うか、さっきからずうっとこれを見ながら執筆してるのだが)。92年ぐらいまでは「チェック・ユア・マイク」や「ゴールド・チャンプ」の様なMCコンテストが盛んに開催されている。裏を返せばそれだけアーティストにとって有効な現場が少なかったのでは、とも言える。92年頃といえば、全国にサウンド・システムが急激に増殖し始めた時期だった。しかし現在の様に、各地のサウンド・クルーが全国を回れるツアー・ロードは確立されていなかったし、それだけ地方同士の交流も少なかったといえる。では、93年頃以降にこのネットワーク化を進めたものは何だったのか? それは「日本人ダブ・プレートの現場での実用化」と「セットを建造するクルーの増加」ではなかっただろうか。「実証作業の拡大」が始まったのである。
前述した様に、V.I.Pの様に日本人作品の頒布に尽力した存在はあっても、実際、レコーディングの機会を得られるアーティストはまだまだ限られていた。それでも多くのマイク持ちが″自分の曲を録音物にして、それをクラブで聞きたかった″のだ。しかも自ら手製のサウンド・システムで。レゲエ特有の録音物、″ダブ・プレート″は、その格好のメディアとなった。「即、録れる」「即、聴ける」という手軽さ。この頃はカッティングのためにジャマイカに行かなければならないという問題もあったが、それだけジャマイカを訪れるクルーは増えていたのだ。94年頃にはセットを保有するクルーもかなり増えていた。同年9月にジャマイカで発足し、逆輸入的に日本に作品を送り込み始めたジャップジャムの活動も、大いにシーンを刺激したはずだ。同年に爆発的な大ヒットを記録したブギー・マンの「パチンコ・マン」も、ジャパニーズ・レゲエを広く一般のリスナーのレヴェルにまで知らしめる結果をもたらした。その余韻の中で、94年12月にG'sファクトリーよりリリースされたナニワレゲエのショウケース『レゲエちゃうの?』(ダメ・G、ブギー・マン、カ・カ・ティー・マン、リトル・チビ、ハッピー、ファット・サンタ、ナッティ・キング、メジャー・ウェポン、シスター・モンキー・Uらを収録)も、アーティストの裾野を広げるのに一役買い、関西シーンの層の厚さを全国に印象付けた。こうした底辺拡大に伴い、それまで「どこそこのクルー所属」といったニュアンスに拘束されがちだったマイク持ちたちが「他のサウンド・クルーのためのダブを録る」という、更に開けたフィールドで活動を始める様になる。と同時に各サウンド間の交流も深まっていき、各々の地元を行き来する様になる。こうしたことが、現在のシーンを確立する素地になっているのだと思う。
95年は、ある意味、ジャパニーズ・シーンの第一次のピークを迎えた年だった様に思う。6月にはブギー・マンが、アルバム『Big
Time』をテイチクよりリリース。同じ6月に初期の長期武者修行組の代表格であるアキ&ソルトフィッシュの作品が初めてCD収録されたチャイナマン・プロダクションのコンピ『Hits
A Go Buss』(アキソルの他に、パパ・ボン、パパ・ユージ、マユ、マチャコ、ベイビー・ベイビー、キング・サト・Bらを収録)が、7月には御大ランキン・タクシーの3枚目となるアルバム『Ruff
Biz Today』がリリースされた。こうした盛り上がりを象徴する様に、9月には日本のサウンド・システムによるイヴェントが、本誌「Riddim」の創刊150号記念企画として開催された。 「Riddim Clash」と冠されたこのイヴェントは、当時名の通っていた6つのサウンド・システム(タクシー・ハイファイ、V.I.P、エクスタシー、ロック・デザイア、ターミネイター、ブレインバスター)を、川崎クラブ・チッタに集め、クラッシュさせるという企画で、開催前からかなりの話題を呼び、当日現場を訪れた読者も多いことだろう。盛り上がりの気運は更に上昇する。そして前述した様に、10月には浪花男『ブレイクしそう』が、11月にはV.I.Pによるコンピ『志〜The
Best Of Japa-nese Reggae』が、相次いでリリースされたのであった。 「Riddim Clash」と冠されたこのイヴェントは、当時名の通っていた6つのサウンド・システム(タクシー・ハイファイ、V.I.P、エクスタシー、ロック・デザイア、ターミネイター、ブレインバスター)を、川崎クラブ・チッタに集め、クラッシュさせるという企画で、開催前からかなりの話題を呼び、当日現場を訪れた読者も多いことだろう。盛り上がりの気運は更に上昇する。そして前述した様に、10月には浪花男『ブレイクしそう』が、11月にはV.I.Pによるコンピ『志〜The
Best Of Japa-nese Reggae』が、相次いでリリースされたのであった。
しかし、こうした日本語レゲエの盛り上がりとは裏腹に、国内の洋楽マーケットにおけるレゲエのシェアは95年後半より、突然減少傾向に向かう。明確な理由は判然とはしていない。前年の94年から95年前半までは絶好調であったのにも関らずだ。しかし、それはあくまで「洋楽マーケットにおけるレゲエ」の話しである。もちろん影響が無かったとは言えないが、ジャパニーズ・レゲエ・シーンは、更に拡大していく。実際、アキソル、パパ・ボンといった初期の長期武者修行組の帰国と国内での活動開始、トキワを始めとする新世代の台頭など、これからの5年間の方が、より多くの作品が発表されているのである。「発見」による「提示」を受け、「実証」による「経験」を蓄積し、「成熟」していく次の段階に突入していくのである。
(文中、敬称略。限られた誌面の中で、リリースされた作品に触れることに主眼をおいたため、地方、特に大阪シーンを牽引されてきた方々の詳細に触れることが出来なかった。キラサン・ムーヴメントを始め、現在の大阪シーンの礎を築いた多くの先達たちが80年代末から活動していたことを、ここに付記しておく。)
|
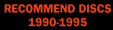
 「This Is」
「This Is」
Hardcore Reggae
[Alpha Enterprise/ YH-1007]
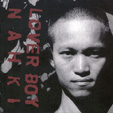 」
「Lover Boy」 」
「Lover Boy」
Nahki
[Alpha Enterprise/ YHR1035]
 「Hard Man Fi Dead」
「Hard Man Fi Dead」
V.A
[日本コロムビア / COCA-10183]
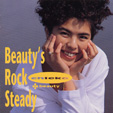 「Beauty's Rock Steady」
「Beauty's Rock Steady」
Chieko Beauty
[Sony/ SRC2-9]
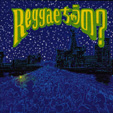 「レゲエちゃうの?」
「レゲエちゃうの?」
V.A
[Sony / SRCS3102]
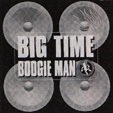 「Big Time」
「Big Time」
Boogie Man
[テイチク / TECN-25306]
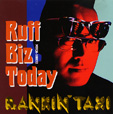 「Ruff Biz Today」
「Ruff Biz Today」
Rankin Taxi
[Media Remoras / MRCA-10032]
 「V.I.P. Presents 志」
「V.I.P. Presents 志」
V.A
[Sony / SRCL-3395]
 「ブレイクしそう」
「ブレイクしそう」
浪花男
[G's Factory / SRCL3339]
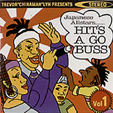 「Hit's A Go Buss」
「Hit's A Go Buss」
V.A.
[Alpha Enterprise/ YHR1125]
|

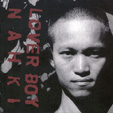 」
」