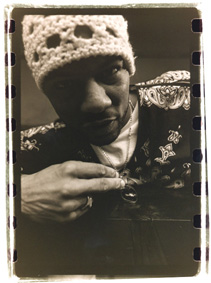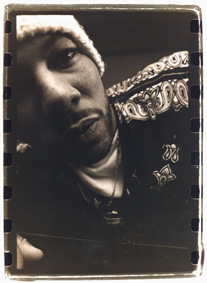|
コモン、もといコモン・センス。「常識」「分別」を名にするほどの良識派として鳴らす。だからこそ、ちょっと変わっている、と長年思ってきた。ファースト『Can
I Borrow A Dollar』とセカンド『Resurrection』は名作、97年の『One Day It'll Make
All Sense』に至っては傑作との評判を持つ。それに甘んじることなく、新作『Like Water for Chocorate』は生楽器やアフロ・ビートの導入などまた違う角度から作られた作品だ。この3年間で変わったこと、成長したことについての自己分析から。
「自分自身についてと、音楽についてより深く理解できたと思う。あちこちへ旅して、色々な音楽に触れて精神的にも広がりが持てたし、ミュージシャンたちと交流する中で学んだことのカタログがこのアルバムだ。それから、正しく、前向きでいることは大事だけど、必ずしも完璧でいる必要はないと気付いたんだ。だから、このアルバムにはリラックスした雰囲気やユーモアも入れた」
アルバム・タイトルは92年に出版されたベストセラーから取っている。メキシコの女流作家の作品で、料理のレシピをアクセントに、南米らしい幻想的なファンタジーが織り込まれた恋愛小説である。面白い本ではあるが、ラッパーがタイトルとして使うにしては少々軟派な感じもする。コモンは「まずタイトルがファンキーでフレッシュだったから」と説明する。
「水は俺の星座(水瓶座)、チョコレートはソウルを表してぴったりだと思ったんだ。それから、これは自分が愛する人と思いを遂げられない女性が主人公で、彼女がその思いを込めて料理をすると、それを食べた人が不思議な体験をする…このアルバムを聴いた人がそんな風にとってくれたらいいな、と思って名付けたんだ」
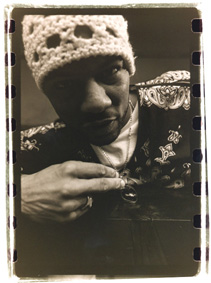
今回、目を引いた変化はプロデューサー陣営だ。同じくシカゴ出身で、コモンといえば彼、というくらいセットだった感のあったNO-IDの作品が一切ないのである。
「今回、俺が欲しかったフィーリングをNO-IDがそれを持ち合わせてなかったんだ。別にケンカしたとかじゃなくて、それぞれのやりたいことを認め合った結果だよ」
その代わりに登場したのがThe Soulquarian's。ルーツのクエスト・ラヴ(エグゼクティブ・プロデューサー)とディアンジェロ、それから後期ア・トライブ・コールド・クエスト作品で知られるジェイ・ディーを含むスーパー・ユニットだ。
「個々ですでに機能していたり、すでにほかのグループの一員だったりするけど、みんなが集まった時にソウルクェリアンズとなるプロダクション・チームなんだよ。たまたまみんな水瓶座で、すごい才能の持ち主の集団だよね」
実はクエスト・ラヴだけでなく、トランペットのロイ・ハーグローブなどミュージシャンもディアンジェロの2作目『Voodoo』と重なっている。スタジオも同じならレコーディング時期も重なっており、並々ならぬコネクションがあるとにらんだのだが。「確かに、お互いのセッションに行き来することもあったよ。ミュージシャンが被っているから同じフィーリングがあるのも本当だ」と認めた。ディアンジェロも昨年、私がインタヴューをした時、共感するアーティストとしてコモンの名を挙げていた。
「もちろん、違いもたくさんあるし、俺がヒップホップ界のディアンジェロになりたい、とか言うわけじゃないけど(笑)。俺達はみんな、音楽にすごく愛情を持っていて、そこに共通点があると思うよ。ただ、音楽家としてはディアンジェロやアミーア(クエスト・ラヴ)の方がずっと上だけど。楽器を使える点でもそうだし、あの2人には天賦の才がすごくある。俺はミュージシャン・シップを育てている最中のヒップホップ・アーティストなんだ」
コモンはシカゴからNYへ活動拠点を移している。2年ほど前からルーツのブラック・ソートやブラック・スターとつるんで、あちこちのステージに立つ姿が目に付いた。新作にはルーツのメンバーやモス・デフが当然のように参加してもいる。ひょっとして、90年代後半のネイティブ・タンみたいなもの?と尋ねたら一笑に付されてしまった。
「彼らとはごく自然に行動を共にしている。俺は音楽を通して、愛や、向上、前進、ブラック・カルチャー、闘いなんかを表現したい。そういった関心事を彼らと共有しているんだ。ルーツはルーツの音があるし、モス・デフのアルバムと俺のアルバムはまた違ったものだけど、それぞれが急進的に(音楽的に)進んでいる点は同じだ」
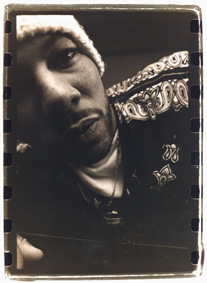
新譜の特徴2。キューバに亡命した元ブラックパンサー党のアサッタ・シャクールやラゴス出身のアフロ・ビートの雄、フェミ・クティに捧げた曲があること。超大国アメリカの人々は一般的に海外に目を向けることが少ないだけに、印象深い試みである。
「彼女の伝記を読んだ後であの曲を書いたんだ。キューバのヒップホップ・フェスティバルに行った時に、実際に会ったよ。俺は、神や愛について常に探求するタイプだけど、ここ最近は様々な場所で経験を積んで、色々な方向に成長できたと思う。つまり、外国に行ったり、新しい人々に会ったり、本を読んだり、映画を観たりといった体験を自分なりに解釈して人間としての成長に生かしたんだ。アフリカやキューバからの音楽を取り入れるのも、″アフリカからのブラザーを入れたらイイかな″ってことじゃなくて、アフロ・ビートを聴いてピンと来たから、自分が楽しんで、影響を受けた音を俺なりに演出したんだよ」
昨年、ルーツのショウでエリカ・バドゥがダイヴしたあと、コモンがブレイクダンスを披露するというハプニングが起きた。前作に引き続きエクセキューショナーズのミスター・シニスタをフィーチャーして、DJについても理解を示している。コモンにとって、ヒップホップ・カルチャーとは何だろうか?
「贈り物。自分たちを表現するために与えられた最高の方法だと思う。黒人やヒスパニックがコミュニティーに向けて表現するところから始まって、街全体、全米、それから国の外へと広がっていった。今では、ほかの国の人もそれを使って自己表現しているように、ほかの文化を接続する役目を果たしているよね。日本語が喋れなくても俺が日本に行けて、みんなも俺が言っていることを部分的でも理解してくれるわけだろ? ヒップホップは世界を変えていく革命的な手段だ。実際、今までも変えて来ているし。俺は、常に新しくて違ったものを提供していくことで(MCとしてヒップホップ・カルチャーに)貢献している。シカゴ発のエッジとか、ファンキーでソウルフルなモノを音楽に注入することとかでね。あと、俺は真実を語ることを恐れない。想像力ももちろん使うけど、本物であることでも貢献していると思うな」
うーん、エライ。ここで以前からの私の疑問が頭をもたげる。ラスタ系アーティストにも感じているのだが、いつでもコンシャスでいるのは大変、というか不可能なのではないだろうか?
「ハハハ、俺はコンシャスだけど、いつでも完ぺきでいようとは思ってない。すべてをシリアスに捉えないようにしてるし。コンシャスで革命的で、向上心が強い人間だって、時々キレて口汚くなったり、女性とゆっくり過ごしたいと思ったりするのは当たり前のことだと思うんだ。コンシャスというのは現状に関心があって、意識が高いってことなんだからさ。このアルバムでも言っているように″知的であると同時にセクシーでありたい″ってわけだ。みんなの期待を裏切りたくないけど、矛盾が生じる時だってあるよね」
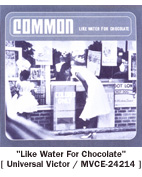 納得。達観しているわけだ。価値観を共有する仲間と作った新作に余裕が感じられたのは気のせいではないようだ。クレジットに「手拍子」なんて入れる茶目っ気も出てきたし。最後に、日本のB・ボーイのために、優れたリリシストとして有名なコモンの作詞方法を紹介して締めくくろう。 納得。達観しているわけだ。価値観を共有する仲間と作った新作に余裕が感じられたのは気のせいではないようだ。クレジットに「手拍子」なんて入れる茶目っ気も出てきたし。最後に、日本のB・ボーイのために、優れたリリシストとして有名なコモンの作詞方法を紹介して締めくくろう。
「ゆったり座って音楽が俺の中から何か引き出してくれるのを待つ。トラックを聴いてから詞を書くことが多いな。だから、ドープなビートが来るとすごく書きやすい(笑)。"A
Song For Assata" や "Payback Is A Grandmother"
みたいに初めからコンセプトがある場合もあるけどね。書き留めないで、何回もくり返し口に出して音に合せて行くことで組み立てていくよ」
|