

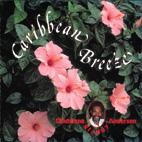
96年10月、僕はキングストンのメインストリート・スタジオ前の道路に停めた車の中にいた。アックスマンから10日間レントしてもらった白のニッサン車は、ターボ付きとはいえ年老いたスピード狂の僕をまあ満足させる程度のもので、エアコンのぶっ壊れたクソ暑い車の中でふき出す汗を拭いながらグラディ、スリラーUと僕の3人でグラディが持ってきたカセット・デモを聞いて「あーだこーだ」とやっていた。そう、グラディの曲提供とプロデュースでスリラーUのアルバムに1曲参加させようという相談だ。
1934年にセント・アンドリューに生まれたグラディはその後トレンチ・タウンに移り、50年代末期から伯父のオウブレイ・アダムスの手ほどきでピアノを習得しカリプソ、メント、R&R、R&Bなどをプレイしてきたのだが、その才能を見抜いたデユーク・リードによりトレジャー・アイル・レーベルを始めとしてスタジオ・ワンやミス・ポッテンジャーのビバリーなどで数えきれないほどのセッションをしてきたミュージシャンである。スカタライツやドラゴニアーズがツアーなどを始める前のオリジナル・メンバーでもあるし、レボリューショナリーズ、ルーツ・ラディックスなどとも深い関係にある。プロデューサーとしてのクレジットこそ見つけることは少ないが、彼いわくトレジャー・アイルの多くは彼のプロデュースであるという。何度かいっしょに仕事をしたが的確にアレンジやコーラスの指示を出す信頼のおけるベテラン・ミュージシャンであった。まさに″ジャマイカン・ミュージックの父″と呼ばれるにふさわしい才能の持ち主である。
72年にファースト・アルバム『It May Sound Silly』(日本盤『カリビアン・サンセット』)以来インスト・アルバムを4枚(DUBを除く)と歌もの2枚(1枚は現在廃盤の『Don't
Look Back』)が出ている。シンガーとしては「Just Like A River」がジャマイカン・チャート2位、『It
May...』の中のシングル「リーヴィング・ローマ」が英チャートで6位になっているというその長く輝かしい音楽人生を考慮すれば、決して多くのアルバムを残している訳ではないが、紛れも無きジャマイカン・ミュージックのキィマンの一人だ。
そんな彼にスリラーUのアルバム『Youth』の最後を飾る曲をやってもらおうという計画だ。そして半年後に出来上がった「ステイ・イン・パラダイス」という曲はスリラーU自身が一番好きだというほどの曲に仕上がった。
今年の6月、とても天気の良い日にロンドンのポートベローの雑貨屋の前をMoomin達と歩いていたら聞こえてきたのがグラディの『It
May Sound Silly』だった。世に何万とあるアルバムの中でこの店の主人がこれを偶然かけていた所に遭遇したのだ。久々に聞くあのゆったりとしたピアノ・プレイ。ジャマイカ人らしい主人に「いいのを聞いてるね」と嬉しくてつい声をかけていた。
日本に帰った僕は、彼の大切な5枚目のアルバム『カリビアン・ブリーズ』を引っ張り出し廃盤にしてしまっていることを大いに反省した。勿論、僕にとってもグラディと共に深夜のタフ・ゴングでディーン・フレーザーのサックスやボビー・エリスのトランペットに加えクリーヴィに生ドラムを叩かせて作ったずっと大切にしていた宝物だから、いつの日か再発しようと思ってはいたのだが遂に決行。
そして、ここに音楽好き諸兄に貴重なコメントを頂いた。Nuff Respect.(石井 "EC" 志津男)

●井出 靖(KING COBRA)
「It
May Sound Silly」は本当に好きな曲のひとつだ。誰にでもあるだろう自分好みの音、それがこの曲にはすべてある。やさしく、つまびくピアノ、あまりにも美しすぎるストリングス…。
すごく切ない、自分でもどうしようもなくなる位、胸がキュンとなってしまう。それはアルバム『カリビアン・サンセット』を初めて聞いてからこの10年ずっと変わらない。
石井さんからこの原稿を頼まれてこの『カリビアン・ブリーズ』を久しぶりに聞いたけど、僕の中でのグラディがそのままいた。甘く切ない、6曲目のタイトルじゃないけど「Mellow
Song」という言葉がピッタリだ。しかし、ロック・ステディに「Mellow Song」というタイトル。この辺りのセンスも僕がグラディを好きな理由のひとつかもしれない。
●こだま和文
遠く離れていてもその人のことをずっと好きでいるなら、その人は心の中で生き続けるしいつも身近にいてくれる。と僕は思っている。
グラディのピアノの音色は湧き水のように瑞みずしく、鳴りのいいスティール・パンのようにやさしくたくましい。そして、年輪を重ねても青々とした新緑をつける樹のように僕をやさしくさせる。
遠く離れた良きジャマイカを思い、愛する人を想う。
●Tico(Little Tempo)
グラディのピアノとカリブのリズムが合わさるとスカ、ロックステディ、レゲエといったすばらしい音楽が生まれ、その音世界は美しく、哀しい情感に満ちている。そんなジッちゃんのアルバムはいつも僕達をやさしい気分にさせてくれるのです。
●松井 仁(Determinations)
先日、オーバーヒート石井氏に大阪で会った時に渡されたのが、この作品のサンプル・テープであった。まさか、その再発につき原稿依頼がやって来るとは…。まいった。
さて、″グラディ″といえば石井氏のライナー・ノーツに記されているようにジャマイカ・ミュージックの歴史そのものと言っても過言ではなく、特に、スカ、ロック・ステディ期における名演の数々等、今だ自分がデタミネーションズでプレイし続ける源の一部となっている事を、今テープを聞きながら改めて感じる次第である。と同時に、現代のようにある種″マッチョな思考″が実行されているような場所でこういった形の表現方法がどこまで深く愛され続けていくものなのか疑問ではあるが、その一聴してすぐ彼と分る″変わらない″鍵盤技法は、時おり実生活者において″変われない事″へのやましさを感じてしまう自分には、むしろ音楽うんぬんでは無い所で″よりどころ″となっている。
●山名 昇
昨晩の衛星で、コステロがバカラックについて「彼は中道なイージー・リスニングの作曲家なんかじゃないぜ」と言っていた。コステロってマジ過ぎんだよな。中庸でイージーで何が悪いの。このグラディなんて超イージーじゃん。午後のお茶沸く間に聞き直してるけど、文句あんのかよ。グラディが気持ち良さげにピアノ弾いてくれるの、聞いてればいいの。気持ち良くお茶が飲めるような人生送りなさいって言ってるだけだよ。哀愁ですって? あるに決まってんじゃん、じいさんだもん。そんなことワザワザ書く奴の人生に愛も何もないだけさ。ここにはリズム・トラックの謎もないしね。ムーディーズの音源のリイシューじゃなくて、当時の新録だってことに意味があったけど、今から聞く若い衆には関係ありません。歴史に残る名盤、のわけないじゃん。このピアノの音が、そんな主張してないところがいいの。それでいいの。
●渡辺浩司(Ska Flames)
一目見て性格のわかるという人がいる。グラディは正にそういう人です。人の良さ、やさしさがそのまま音に現れている。そんなグラディの作品が悪いはずがない。これを聞いてグラディそのものをわかって欲しい。
僕がグラディに初めて会ったのは、スカタライツの初来日の時だった。ピアノ担当で来ていたグラディは、正式なスカタライツのメンバーではなかったが、他のメンバーに楽譜を書いて渡していた。ジャマイカにも音楽をちゃんと勉強している人がいるのだと、この時感心した。
音楽的にも優れたグラディの作品、古い物も当然いいのだがこれからにもまだまだ期待したい。